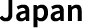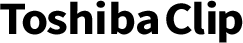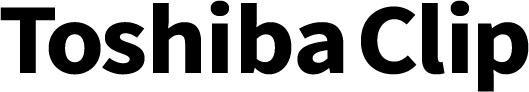保守サービスに秘める自信と誇り -社会インフラを支えるインフラ編-
2019/01/23 Toshiba Clip編集部
この記事の要点は...
- 世界中で電気の安定供給を支えている発電所保守サービスの仕事とは?
- 未曾有のトラブルも乗り越えたそのスピリット
- 火力発電所の保守サービスの本質は…「社会インフラを支えるインフラを守る」である


1枚の世界地図がある。日本はもちろん中国、アメリカ、カナダ、イタリア……世界各国の火力発電所にピンが立てられている。これは、東芝エネルギーシステムズ株式会社 火力・水力事業部 火力サービス技術部所属の高木健太郎氏が20年以上にわたって火力発電所の保守サービスに携わってきた発電所の数々だ。
自分が携わった仕事を世界地図で一覧できることがこの仕事の醍醐味だという。高木氏はこれまでの仕事を振り返りつつ、世界の発電所に目を走らせた。

東芝エネルギーシステムズ株式会社
火力・水力事業部 火力サービス技術部 部長 高木健太郎氏
「アメリカではレンタルトラックを駆って何百kmもかけて発電所を目指しましたし、アフリカではシマウマが飛び跳ねるサバンナが現場だったこともありました。今はGPS対応のスマートフォンで簡単に目的地に辿り着けるようになりましたが、私が海外赴任していた2003年頃は大変でした。何しろ、住所がない発電所も珍しくなかったですから。『Route 254 Northeast』――254号線の北東、というわずかな情報を頼りに現地に向かい、遠くに立つ煙突を見つけて『あ、あそこだ!』と一安心。そんな経験がたくさんありますよ」(高木氏 以下同)
土地が広大な国では、原野のただ中に火力発電所が建てられることも多い。当然ながら、建設時には地番もない。つまり「住所がない」のだ。困難なアクセスから、生活を支えるインフラの重みを高木氏は感じていたという。
1年かけて納入した機器のサイズが合わない!? アメリカでの大トラブル
そもそも、火力発電所の保守サービスとはどのようなものなのか。長期間にわたって信頼性の高い発電を続けていくため、発電所にも定期的な保守点検は欠かせない。それは私たちの健康診断、車における車検と同じだ。
ただ、火力発電所のライフサイクルは30~40年以上にも及ぶ。蒸気タービンなどの大型機器の更新時期をあらかじめプランニングし、長期的な視点に立った運転保守・管理計画をお客様に提案していく必要があるのだ。
「東芝は火力発電プラントの開発から設計製造、据付、保守サービスまでワンストップで手掛けていますが、古い火力発電所ほど保守サービス業務が重要になるんです。火力発電所は、各国の法令であったり電力会社の自主規制により定期的な点検が実施されます。また、蒸気タービンなどの機器はオーダーメイドだったり、特殊な素材を使っていたりして、納期が長くかかるものも少なくありません。寿命がきたり、壊れたりする前にあらかじめ修理、交換を施す『予防保全』も重要です。発電所が安定して電力を供給できるために、保守サービスを長い視点で提供していく。それが私たちのミッションの根本にあるのです」

2005年 フロリダ州にて
これまでの発電所、プラント行脚を懐かしく思い起こす高木氏だが、保守を手掛ける者として、決して忘れられないターニングポイントがあるという。それは、アメリカでの蒸気タービンローター更新プロジェクトだ。
「1960年代に他社が納め、運転開始から長い時間を経たプラントでした。私たちは、そこに最新技術を盛り込んだローターへの更新を提案しました。より高効率であったり、環境負荷が小さかったりと、最新の火力発電機器には多くのメリットがあります。粘り強いセールス活動の甲斐があって受注できましたが、もともと他社が納入した蒸気タービンの大規模改造を実施するのは会社としても当時初めてのトライです。喜びの裏に大きな課題もありました」
課題とはなにか。それは東芝がそのプラントの設計図面を持っていなかったことだ。新ローターを製作するためには、既設機の正確な寸法が必要になる。時には検査員を手配する時間もなく、高木氏自身がプラント内に入り、細かな計測作業を行うこともあったそうだ。
「セールスエンジニアとして現地に足を運んだ私ですが、まさか命綱をつけてプラント内に入るとは思いませんでした。ただ、もともと機械の設計者ですから、楽しく作業をし、計測した寸法を工場の設計部門に送ったものです」

2006年 ミネソタ州にて
1年後、完成したローターが現地に輸送されてきた。ピカピカのローターが誇らしい。しかし、いざ据え付けるという時に高木氏は青ざめた。
「ローターのボルトの位置が既設機の位置と大きく合わないんです……。分かった瞬間、緊張とパニックで吐きそうになったのを覚えています。隣にいた同僚のアメリカ人エンジニアの『おい、大丈夫か?』という声が遠く聞こえました」
電気を止めるな! 保守サービスエンジニアの合言葉を胸に
新ローターのボルトの位置が合わない。これでは納品ができず、火力発電所の再稼働ができない。高木氏の脳裏に様々な解決策が浮かんでは消えた。既存のローターに戻すか? いや、古い部品はもうスクラップになっている。新しく作り直して再納品? いや、このローターを設計し、作ってから納品まで1年以上かかっている。再びそれだけの時間はかけられない。一体どうしたものか――。
「日本の工場の設計部門には気心が知れた同期の設計者がいました。彼とコミュニケーションを取り、何か解決策がないか、必死に頭を絞ったのです。私はアメリカで、彼は遠く離れた日本で、睡眠時間を削りながら、チームとして24時間ノンストップで策を検討し続けることになりました」
様々な方向から解決策を探ってはみたが、位置の大きな違いにお客様である発電所のエンジニアも高木氏も言葉がない。「どう調整してもこのままでは無理だ」というのが共通した見解だった。しかし、ギブアップするわけにはいかない。
なぜか? それは、このローターが火力発電所を動かす大事な心臓部だからだ。出力80万kW。この地域に住む多くの人たちの生活を支えている。その重みを、高木氏は痛いほどに感じていた。

蒸気タービンローターのイメージ
「お客様にお詫びしたり、ペナルティを課されたりして済むなら、まだいいでしょう。でも電気は止められない。私たち保守サービスを手掛ける者にはそんな使命感があります。絶対に無理だと思っても、泣いても笑っても、80万kWの発電を止めるわけにはいきません。日本にいる設計部門では同期が頑張ってくれている。だったら、現場では私が頑張らなければ。発電所の蒸気タービンをなんとか回すんだ。そんな思いが私たちを支えていました」
太平洋を挟んで協議、検討を重ねた結果、現場で部品を加工し、必要な修正するというウルトラCの解決策が導き出された。設計部門の同期には、修正・加工を施しても機能と性能を担保できるアイデアがあった。
一連の解決プランをお客様に承認してもらい、据付のスケジュールも現場でマネジメント。結果として当初の工事工程を守って納品できた。お客様が送ってくれた感謝レターは、今でも高木氏の宝物だという。
「このようなトラブルが起こったら、ほぼ納期がずれ込むもの。だけど、東芝は守ってくれた。大変感謝している――そんな文面が綴られていました。私もこの経験に感謝している面があります。解決を目指すやり取りを通じて、『保守サービスの本質』とでも言うべきものを身をもって実感できたからです」
電気は止められない、電気を止めるな――それは、社会インフラを支える者の合言葉だ。目に見えないところで人々の暮らしを支える仕事である。くじけそうな高木氏たちを奮い立たせたのは、保守サービスエンジニアの使命感だった。
「電気は水道やガス、交通機関などと並列で『ライフライン』とくくられますが、水道もガスも、そして電車や交通信号も電気がなければ稼働できず、インフラとして機能しません。人々の暮らしを支える社会インフラを、さらに下支えする。それが火力発電所保守サービスの本質だと、私たちは考えています」

![]()