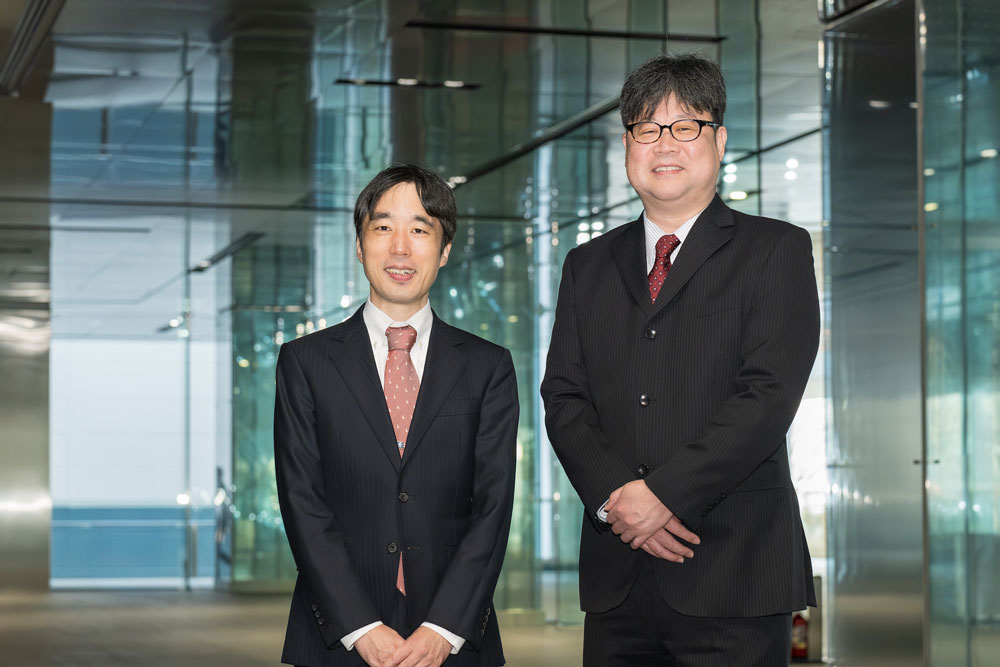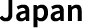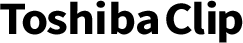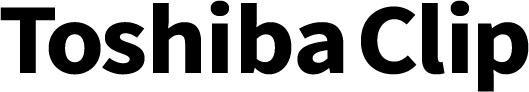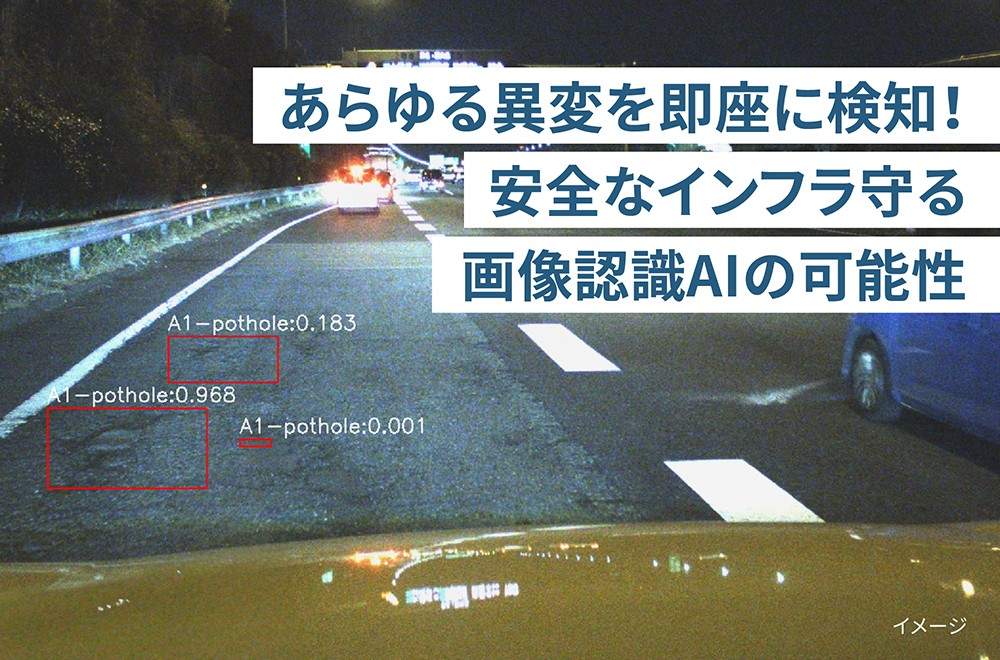匠の技をAIが継承—輸送計画ソリューションがつくる鉄道運行の新常識
2025/03/18 Toshiba Clip編集部
この記事の要点は...
- 正確な鉄道の運行には多種多様な要素を考慮した計画が必要だが、これまで限られた匠の技によって支えられてきた
- 鉄道輸送計画を支える匠たちの高齢化によって、人に頼らず短時間で効率的な運行計画を作成するTrueLine®を開発
- 複数の最適化AIは、今後航空機やトラック、製造業やエネルギー業界など様々な領域に活用が期待される

朝夕の通勤ラッシュ、長距離移動を支える新幹線、都市部を網羅する地下鉄。日本の鉄道は、世界に誇るべき正確さと効率性を兼ね備え、人々の生活に欠かせないインフラとして、社会や経済を支えている。
鉄道の輸送計画は、時刻表の形で我々が目にする路線ダイヤを始め、車両の運用および乗務員のスケジュール管理、さらには保守作業やイベント開催など、非常に多くの要素を考慮した上で、安全に定時運行を実現するために策定されている。その作成作業は非常に複雑で、熟練の技術者たちの長年の経験と勘、そして膨大な知識によって実現されているという。
東芝は、こうした匠の技とも言える輸送計画業務を、直感的なマウス操作で実現する輸送計画ICTソリューション「TrueLine®」を開発した。
正確な鉄道運行、実はとっても大変!?– 輸送計画ICTソリューション「TrueLine®」で解決できることとは?
輸送計画の作成は、複雑なパズルを解き明かすような作業である。わずかな変更が全体に波及し、遅延や混乱を引き起こす可能性を孕んでいる。これまで、熟練の技術者たちは、様々な要素を巧みに調整しながら、最適な輸送計画を導き出してきた。
「TrueLine®は、AIの力で輸送計画業務の効率化を支援するシステムです。AIが大量のデータを分析し、最適な輸送計画を高速かつ正確に作成します。これにより、輸送計画作成の効率化、人為的ミスの削減、そしてなにより安全な輸送計画の立案に貢献します」
そう説明するのは、東芝で長年鉄道事業に携わり、TrueLine®の開発も主導してきた東芝デジタルソリューションズ株式会社の久保英樹氏だ。

列車のダイヤ作成をする際は通常、縦軸には距離や駅名などが入り、横軸は経過時間となるグラフ上で線を引く。駅間の距離や停車時間などにより線の角度が少しずつ異なるためガタガタした斜線となるが、この線を鉄道業界では「スジ」と呼んでいる。
従来のシステムでは、列車の発車時刻を後ろに数分ずらす場合は、一つひとつ駅ごとに確認しながらスジを書き換える必要があった。各駅で混雑状況などが異なっていたり、他の接続線へのダイヤに影響しうる前後の列車との調整が必要だったりするためだ。一箇所を書き換えても以降のダイヤが連動してずれるわけではないので、非常に手間のかかる作業を強いられていたという。そこで、久保氏はこう続ける。
「TrueLine®であれば、マウスで“スジ”そのものを選択し、ドラッグしてずらすだけで、以降のダイヤにも自動的に必要な変更が反映されるので、調整も含めてほんの数秒もかかりません。もちろん関連付けられているその他の路線との最適な調和を取った上で、もっとも安全な選択肢としてスジが描かれます」(久保氏)
次の図は、一般にダイヤと言われる運行図表と呼ばれる列車の運行計画を表した図表である。
TrueLine®では、マウス操作によって特定の駅の出発時刻を変更するだけで、それに合わせた運行計画に変更された「スジ」が自動で生成される。
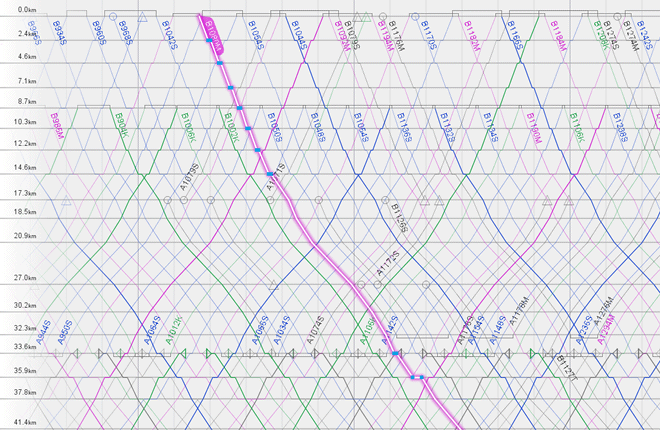
駅での停車時間をマウス操作で変更するだけで、その後の駅の到着時刻、停車時間などを考慮した新しいダイヤを「スジ」として描き出してくれる。
サービス開発の際、力を入れたのは「操作性」だ。手書き感覚の入力に加え、専門家でないユーザーでも、複雑な輸送計画業務を短時間で正確にこなせるようデザインを意識した。その甲斐あって、「グッドデザイン・未来づくりデザイン賞」を受賞した。
こうしたダイヤグラム作成は、TrueLine®によって提供される多くの機能のほんの一部である。機能の全貌紹介については、記事の最後でご紹介する「輸送計画ICTソリューション TrueLine®」の紹介ページに譲るとして、本稿では、TrueLine®誕生のきっかけから、今後何が変わっていくのか、久保氏に迫ってみた。
鉄道畑を歩んできた技術者の熱い想い。銀河鉄道999の世界を目指して
TrueLine®の開発を主導してきた久保氏は、長年東芝において、国内だけでなく海外の鉄道事業にもかかわってきた、言わば鉄道畑を歩んできた技術者である。その久保氏は、日本の鉄道の輸送計画について次のように語る。
「日本の鉄道の輸送計画は非常に効率的です。それを支えているのは、鉄道にかかわる人々の強い思いと、匠の精神(Craftsmanship)です。そこから生み出される成果物は非常に素晴らしく、まさに日本人の良い部分が結晶化した事業と言ってもよいのです」(久保氏)

しかし、近年、輸送計画を担っていた限られた技能者達の高齢化と人手不足が顕在化し、匠の技だけに寄りかかってはいられなくなってきたという。
「これらの課題を解決し、世界に誇る日本の鉄道の安全性と正確さを、未来に引き継ぐために、AIを活用した輸送計画システムソリューションの開発をはじめました。私は幼いころから銀河鉄道999が大好きでよく見ていたのですが、そこではすべての車両が機械でコントロールされていました。そんな世界が、現実でもあればいいのに、と思いました。
運行ダイヤや検査計画の作成、不測の事態への対応など、人の手を煩わせることなくAIの力で実現するTrueLine®を開発したことで、夢見ていた銀河鉄道999の世界に、少しでも近づけたのかなと思いました」(久保氏)
TrueLine®は、すでに複数の鉄道事業者に導入され、高い評価を得ている。導入した事業者からは、計画作成の効率化、人材不足の解消、そして輸送計画の質向上につながったとの声をいただいている。
「今後は、鉄道業界のみならず他の交通機関や物流など幅広い分野への展開も考えています」と久保氏は意気込む。
AI技術開発部門との連携 – 鉄道知識とAI技術の融合
TrueLine®を実現させるための大きなカギが、”AI”である。開発にあたって、久保氏と協力していたのが、東芝研究開発センターのAI技術者である大槻知史氏だ。TrueLine®の開発について、こう振り返る。
「目指したのは、業務効率を上げることでお客様に使いたい、と思ってもらうこと。そして経験の浅い作業者でも、熟練者並みの計画を作成できるようにすることでした」

鉄道に関する深い知識を持つ久保氏と、AI技術のエキスパートである大槻氏。それぞれの専門性を融合させることで、TrueLine®の開発がスタートした。
「輸送計画には、ダイヤ作成のみならずダイヤ乱れの対応や各車両の検査・清掃など多種多様な制約を満たす必要があります。そこでTrueLine®のために独自で開発したのが、最適化AIです。複数の最適化AIを同時に機能させることで、短時間で効率的な運用計画を作成することができるのです。
この最適化技術に関する専門の研究開発部隊を持っている会社はあまり多くありません。東芝では、交通だけでなく、物流・エネルギー・工場など、様々な分野での最適化の実問題に取り組んでおり、膨大なノウハウを蓄積しています。鉄道分野に関しても様々な適用事例があり、ドメイン知識※にも精通している点が強みであったと考えます」(大槻氏)
※ドメイン知識:特定の分野や領域における専門的な知識や情報のこと
しかし、開発当初、鉄道事業について十分な知識を持っていなかった大槻氏は、計画に関する様々な条件の理解に苦労したという。
「現場の熟練者の用語やプロセスに精通すること、熟練者が持つ経験則やノウハウといった暗黙知の言語化、検査や清掃に関わる人員の都合の把握など、業界や現場の状況を細かく知っておく必要がありました」(大槻氏)
久保氏と大槻氏は、現場の熟練者と対面で打ち合わせを重ねていった。
「現場の状況を我々が積極的に知っていくとともに、今お客様がどんなことができていて何ができていないのか、今どんな課題を抱えているのかを読み取り、適切な提案ができなければなりません。例えば『均等な勤務』と言えば、勤務時間を平準化すると考えがちですが、鉄道の世界では『どれだけ長い距離を走ったか』です。鉄道マンは何をもって均等と考えているのかを正しく知ることが重要です。こういった業界の前提となる知識があるのといないのとでは、提案の質が違ってきます」(久保氏)
開発のアプローチは、システムが作成した計画と熟練者が作成した計画と工程を比較し、精度や不足している部分を一つずつ改善することだった。こうしてTrueLine®は、熟練者と遜色のない計画を立案できるように熟成していった。
輸送、製造業、エネルギー。最適化を目指すあらゆる領域での課題解決を目指して
我々が目にする列車は、主に営業線と呼ばれる区間での運行である。この営業線以外にも、整備や留置のための車両基地と呼ばれる場所がある。自動車であれば、ハンドルを切り返せば、隣の車庫に簡単に入れ替えることができるが、列車では、目的の留置線に停車させるためにも、綿密な計画が必要となる。こうした車両基地にもTrueLine®は活躍すると久保氏や大槻氏は言う。
「車両基地運用は、鉄道運用のひずみをすべて引き受けていると言っても過言ではありません。『明日一番に出庫させたいのに、ダイヤ乱れの影響を受けて一番奥の留置線に止めてしまった、急な車両故障で数日間車両を交換したい』など、刻々と変動する条件も、TrueLine®のAIが解決し、基地内の日々の計画を自動で作成することができるのです。」(久保氏)
「車両を先に一番手前の留置線に止めると、車両を迂回しないといけなくなってしまうからやめて欲しい、といった要望を受けAIに条件を追加したこともありました。TrueLine®は、まだまだ発展途上であり、更に限界を高めるための開発を続けています。」(大槻氏)

もちろん、こうした車両基地運用へのTrueLine®の利用は、我々利用者にとっても無関係ではないと大槻氏は語る。
「利用者にとっては、毎日同じ時刻の列車に乗っているつもりでも、車両編成は毎日違うものであることが多いです。毎日、清掃・整備・検査が確実に実施された編成がやってくること。当たり前に感じるその事実の裏には、様々な現場の方々の努力があること、場合によってはAIが活躍していることを、少しでも知っていただければと思います」(大槻氏)

久保氏や大槻氏は、AI技術の完成度については、まだ向上の余地が残されていると考えている。
「TrueLine®は鉄道業界での課題解決にとどまりません。東芝のAI技術を使って、さらなる課題の解決を目指すため、パートナーとして一緒に考えていくようなビジネスの形に進化させていく必要があると思っています」(久保氏)
「最適化AIは鉄道だけでなく、バスやトラック、航空機などの輸送計画から製造業、エネルギー需給計画まで多くの実問題を解決できると考えています」(大槻氏)
大いなる可能性を秘めた輸送計画システムソリューションTrueLine®が、次はどんな未来を見せてくれるのか、楽しみは尽きない。